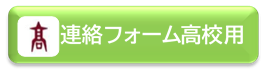高校2学年模擬講義が行われました。
9/9(火)⑥⑦校時、大学で行われる講義等の一端に触れることで、研究機関である大学や学部への知見を深め、大学進学への一層の意識の醸成を図るため、2学年模擬講義を行いました。講師として、弘前大学、青森県立保健大学、八戸学院大学、岩手大学から大学の7名の先生にお越しいただき指導をしていただきました。高校生にもわかりやすく興味深い講義をしていただき、途中休憩を挟みながらも90分の講義はほぼ初めてでしたが、あっという間の時間となりました。
また、本校附属中学校・高等学校の卒業生で、現在東北大学大学院博士課程に在籍している吉村渓冴先生にも、専門で研究されている原子力発電・プラズマについての講義をしていただきました。吉村先生には、前日に来校していただき、東北大学への進学を志望している生徒約30名を対象に、体験談や進路相談を受け付ける機会を設けていただきました。実際に受験の準備をしている受験生からは面接や出願書類での質問がされ、1、2年生の参加者からは高校1、2年生のうちにできる準備などの質問をしたりしていました。活躍する先輩のお話を伺う機会をいただいたことで、参加した生徒からは大学進学や高校生活に対する意欲が高まったとの感想が聞かれました。
【講義一覧】
・岩手大学人文社会科学部人間文化課程 准教授 小野澤 章子 先生
「人を/社会を「測る」ソーシャルリサーチ入門(地域社会学(社会調査法))」
・弘前大学教育学部国語教育講座 助教 市地 英 先生
「役割語について」
・八戸学院大学入試広報部広報課 参与 志村 博 先生
「教職を志す者の心構え」
・岩手大学農学部動物科学・水産科学科 教授 村元 隆行 先生
「食肉の品質を非破壊で分析する(動物資源利用学、食肉科学)」
・弘前大学理工学部数物科学科 教授 守 真太郎 先生
「情報カスケード(統計・応用数学)」
・青森県立保健大学健康科学部看護学科 講師 長内 志津子 先生
「看護における患者との接し方~対象の特徴をふまえたコミュニケーション~」
・東北大学工学研究科博士課程3年 吉村 渓冴 先生
「核融合とエネルギー」
【生徒の感想から】
・学校の先生になりたいと考えていたが、必要な免許や適性について知ることができてよかった。先生になるために普段の勉強をしっかり取り組みたいと思った。
・普段何気なく回答しているアンケートも質問内容、言葉遣い、選択肢など様々なところに工夫がされているということを知っておどろきました。将来は地域と社会のかかわりについて学びたいと考えているので、貴重な経験となりました。
・小学生の時などに学んだ文章が役割語を使っているということを学び、自分の持っている小説を読み直して作者の意図を分析して読んでみたいと思った。
・私たちが普段食べている食肉の流通にも様々な研究が生かされていることを知れたのが良かった。
・人やアリの行動から規則を見つけてグラフや数式に表して、複雑な行動も抽象的に、簡単にすることができるのがとても興味深く感じた。物理と数学の関係を学ぶ数物科学も面白く感じた。
・コミュニケーションを実際にやってみて、普段のコミュニケーションの中にも目を合わせることや手で触れる感覚など会話に欠かせない要素がたくさんあることに気づいた。
・日本のエネルギー問題を解決するために、核融合を使った発電が有効であるということが分かった。同時に、その技術はとても難しく、多くの課題があることも知ることができた。今回講義をしてくれた方のようになるためには、行動力が大切だということが分かった。自分自身の進路決定までのお話をしてくださったことがとても参考になりました。
R7.12.12
「自然災害時(大地震、台風等)の対応について」を更新しました。
令和7年度より、高校の緊急連絡メールは、まなびポケットへ移行しております。
生徒を通じて登録用のID・パスワード、簡易版マニュアルは配付しております。
保護者の方は、専用アプリをインストールすれば、プッシュ通知等が使用できます。
保護者部分まなびポケット操作マニュアル20249.27版.pdf